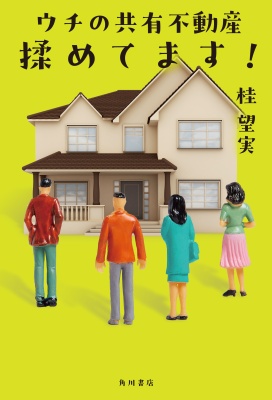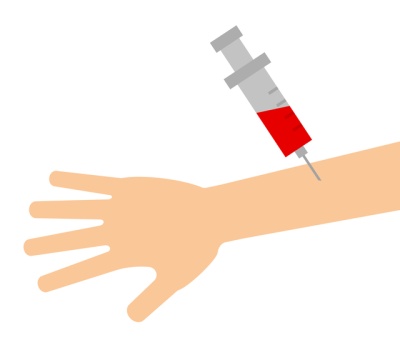メンチカツの専門店情報を新聞で発見しました。
店内で肉を挽き客の前で揚げるという。
紙面の端に小さく掲載されていた記事でしたが、メンチカツ好きの私は見逃しませんでした。
なんでもメンチカツは、卓上コンロの上のフライパンに載った状態で供され、客は断面を好みの加減で焼くというスタイルの定食があるらしい。
メンチカツ好きの私ではありますが、揚げたものを更に焼きたいと思ったことはないので、この定食にはいまひとつピンときませんが、専門店が出来たというのはグッドニュースです。
実家の近くに肉店がありまして、小学生の頃にはよく買い物に行かされました。
なんでも好きなものを買ってきてと言われて店に行く。
ショーケースには様々な品が並んでいます。
それらはパン粉がまぶされた状態。
注文を受けてから揚げるスタイルだから。
私は並んでいる品を一通り眺めます。
一応。
で、結局メンチカツにする。
95%ぐらいの確率でした。

毎度毎度真剣に吟味する風情の小学生の私を見ていた店員は、どう思っていたでしょう。
結局、メンチカツにするんでしょ、と心の中で思っていた気がします。
このように子どもの頃からメンチカツ好きだった私は、今でも好き。
近所のスーパーの総菜売り場で、どれにしようかなと一通り並ぶ品を眺めるのですが、結局メンチカツになる確率が95%程度で、高確率を維持しているのです。
そこまで好きならば、自分でも作ればいいようなものですが、これまでの生涯でメンチカツを自作したことは一度もありません。
母親がそうだったのです。
我が家ではメンチカツは、店で揚げた状態のものを買うと決まっていました。
トンカツやコロッケなど他の揚げ物は、自宅で作ることもありましたが、何故かメンチカツだけは違いました。
私はこれを踏襲し、メンチカツだけは出来合いのものを買っています。
母親の食のスタイルは、子どもに影響を与えるものなのでしょう。
中学生の頃に、級友の弁当箱に赤飯が詰まっていた日がありました。
「どうしたの?」と聞くと、「昨日、おばあちゃんの誕生日だったから、お母さんが赤飯を炊いた」と答えました。
衝撃で箸が止まった私。
赤飯が家でも作れると、生まれて初めて知った瞬間でした。
赤飯が必要な時には、母親は毎度米店で買っていたので、自宅では作れないものだと思い込んでいたのです。
食にまつわる慣習は色々です。
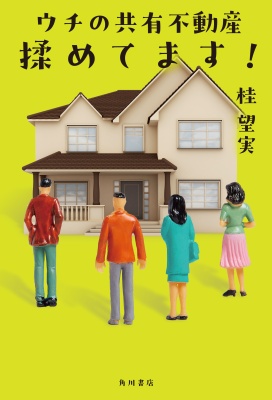
「ボンボンドロップシール」が高い人気を集めているという。
立体シールだそうで、略して「ボンドロ」というらしい。
買い求める人で販売店に行列ができるだけでなく、なかには問い合わせの電話が鳴りやまず、やむなく取り扱いを中止する店まで出ているそうな。

こういうシールのブームの波は、定期的にやってくるんですね。
可愛い→集める→交換する→競争になる→ハマる。
こんな感じでしょうか。
私が小学生の頃はシールではなく、サンリオのキャラクターの推し活が流行しました。
女子は必ずひとつ、推しのキャラをもっていなくてはいけないという決まりがありました。
このルールがいつ、どのように生まれたのかは、はっきりしないのですが、気が付けばそんな事態に。
ひとつ推しを決めたら、そのキャラが付いた筆箱、鉛筆、下敷き、ヘアピン、ハンカチなどをもちます。
仮に推し以外のキャラが付いた物を持つ場合には、クラスの女子全員に「叔母さんから貰ったから」などと説明して歩かなくてはいけなかった。
こうした物は子どもの小遣いでは揃えられないので、当然ながら親に買って貰うことに。
結果、親の収入差が如実に表れていました。
お金持ちの家の子は、なにもかもがその推しキャラに。
それは子ども心にも「やり過ぎじゃない?」と思うほどでしたが、同時に羨ましい気持ちも。
私はリトルツインスターズが推しで、それは母親も充分理解していると思っていたのですが・・・ある日「ほら。これ、着なさいよ」と言って差し出してきたのは、手編みのベスト。
胸にはキティちゃんが。
母親が手編みしたのです。
今思うと、出来は素晴らしかったので、その器用さに感服する思いですが、当時は「なんでキティちゃんなのよ」と怒った。
なんでもリトルツインスターズは、難しそうだったからという理由で、キティちゃんにしたらしいのですが、母親は推しの意味が全然分かっていなかったようです。
嫌がったものの、強引に着せられて学校に行った私。
最初は胸のキティちゃんを下敷きで隠していたのですが、すぐにバレました。
結局、言い訳をして歩くことに。
今なら笑い話ですが、当時はささくれだった気持ちでいたことを覚えています。
新刊小説「ウチの共有不動産揉めてます!」では、個性的な母親が描かれています。
この母親はパンダのグッズを集めるのが好きで、家に大量に飾っていました。
でも動物のパンダそのものには興味がなく、動物園に行ったりはしなかった。
キャラになったパンダが好きだったのです。
そんな推し活もアリなんですよね。
推し活スタイルは色々です。
ミラノ・コルティナ冬季オリンピック観戦を楽しんでいますか?
私はオリンピック観戦を毎回楽しみにしていまして、今回も年明けからワクワク&そわそわしていました。
仕事への影響を最小限にするべく、観戦スケジュールを組まないとな。
と、思いながらテレビ中継の開始時間を調べたら・・・絶望。
午前3時前後の放送が多く、時差を呪いました。
コーヒーがぶ飲みで挑戦するべきなのか、一旦寝てから午前3時に起きた方がいいのか、どっちがいいのか分からない時間帯です。
体力に自信をなくしている昨今。
一度の無理が後を引くお年頃のため、どうすっかなぁと思っていたら・・・NHKが救いの手を。
録画になりますが、試合をフル視聴できる特設サイトを作ってくれると知り、今回はこちらのお世話になることに。
普段はスポーツ観戦は生じゃなきゃと言っている私ですが、これは時差がない場合ですね、やはり。
ということで、今回のオリンピックでは随分とこのサイトで観戦をしています。

そしていつものように、たくさんの感動を貰っています。
王者と呼ばれていた選手がまさかの低順位に沈んだり、ノーマークだった選手が優勝したり。
順当も番狂わせもありました。
負けた時こそ、その人の本来の姿が出るものです。
口惜しさでいっぱいなはずなのに、優勝した選手におめでとうと言葉を掛けにいく選手を見ると、あぁ、一流の選手はさすがだなと感心します。
今回も残念ながらジャッジへの疑問、不満がいくつもの競技で噴出しています。
選手へのリスペクトを形にするとしたら、正確で公平なジャッジを確立することだろうと思います。
AIを導入して、選手たちが一欠けらの不満ももたないようなジャッジ制度を、各競技団体が作って欲しいものです。
それが選手たちの努力に報いることだから。
観戦の合間には、新刊小説「ウチの共有不動産揉めてます!」もお楽しみくださいね。
新刊「ウチの共有不動産揉めてます!」に登場する渚は看護師長。
命を扱う仕事だからミスは許されない。
だから緊張感をもって仕事にあたるように、部下たちに指導しています。
特に厳しくしているつもりはない。
それなのに、気が付いたら渚は職場で孤立していました。
職場の飲み会に一応誘われるけれど、欠席を前提に声を掛けられているのが、アリアリと分かってしまう。
今更仲間に入れて欲しいという訳ではないけれど、なんだかなぁと思っています。
渚の母親が亡くなり、相続した実家の土地と家を、きょうだいで4等分するつもりでいたら、一番下の妹がなんだかんだと言い出しました。
とんでもないことだと憤慨する渚。
そんな我が儘が通るはずもないと思っていましたが、法律上相続人全員が了解しないと売却出来ないため、話は一歩も進まなくなります。
こんな時には長男である兄に、びしっと仕切って欲しいところなのですが、優柔不断で決断出来ない性格のため頼りにならない。
弟は弟で、深く考えずに行動するため、足を引っ張りかねない危うさが。
うんざりしている渚に、追い打ちをかけるように更なる厄介事が。
渚は相続問題に巻き込まれながら、自分の過去と向き合っていくことになります。
渚が最後にどんな決断をするのかまでの過程を描いているのが、小説「ウチの共有不動産揉めてます!」です。
どうぞお楽しみください。
私が年に一度検査のために訪れる病院でのこと。
採血室に入ると初めて見る看護師さんが。
初々しい感じの若い看護師さんです。
それまでの方は辞めたのか姿がありません。
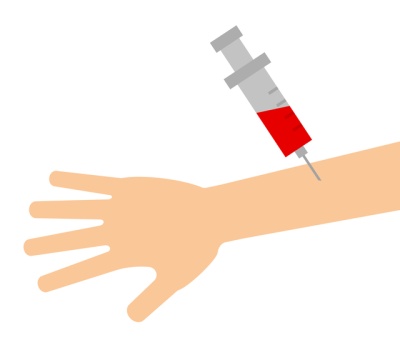
私はセーターを腕まくりして左腕を差し出し、明後日の方向へ顔を向けました。
自分の腕に針が刺さっている現場を見る勇気がない私は、採血の時には大抵顔を背けているのです。
で、ちくっとする痛みを覚悟していると、それがなかなかやってこない。
看護師に目を向けると・・・私の腕に物凄く顔を近づけてガン見している。
そしてその顔には困ったような表情が。
えっ。
「まさか、採血初めてとかって、ことはないですよね」と心の中で尋ねる。
看護師が突然言う。「反対の腕でもいいですか?」と。
不安が大きくなりながらも右腕を差し出す。
また私の腕にぐっと顔を近づけて、真剣な表情。
しばらくそうやってから「はい。こっちの腕で」と言いました。
今、あなたはなにを決めた?
何十年も採血は左腕でして貰ってきましたが、あなたが左ではなく、右で勝負しようと決めた理由はなに?
嫌な予感が胸に広がる。
案の定、これまで経験したことがない強い痛みを感じながらの採血となりました。
そして針が刺さった箇所は内出血してしまい、一週間ぐらい痣が消えませんでした。