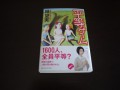行きがかり上の出来事でした。
生まれて初めて、お茶会なる場所に参加することになりました。
茶道なんて、まったく興味のない世界でしたが、一旦参加を決意したならば、せいぜい楽しもうと友人を誘うことにしました。
その友人も、私同様、生まれて初めてのお茶会参加でした。

場所は、都内の某大学内の一角。
人生の大先輩たちが、慣れた感じで和服をお召しになっているのを見て、ヤバいところに来てしまったのではないかと、友人と声を潜めて話し合いましたが、結論が出るわけもなく。
そうこうしているうちに、「さ、こちらへ」などと声がかけられ、部屋に足を踏み入れることに。
そこは和室で、どこに座ったらいいのかと、一瞬途方に暮れかかりましたが、前の人たちの後にくっついて進み、取り敢えず、その人たちの隣に正座をしました。
これは、早めにカミングアウトしておいた方がよかろうと判断し、隣の方たちへ「私たち、生まれて初めてなんです。多分、失礼をすると思いますので、その時には、どうぞ注意してください」とお願いしました。
隣席の方たちは、鷹揚に微笑みました。
その微笑みを、了解と受け取り、私と友人は、緊張したまま開始を待ちました。
部屋には、続々と、人が入ってきます。
と、部屋の入口付近で渋滞がおきだしました。
そうしたなか、座りだしたので、明らかに、入口付近が窮屈そうでした。
すると、中央付近に座っていた人が、「どうぞ、上座にお座りになって」と渋滞の中で座っている人たちに声をかけました。
ですが、10人ほどの人たちは皆「いえいえ。ここで結構です」と答え、上座に移動する気は、誰にもないようでした。
すると、中央付近の人が、今度は私の隣席に座っている人たちに声をかけました。「では、そちらから、ずれていただいて、少しずつ、詰めてはいかがでしょう」と。
位置的にいって、隣席の人たちがずれる先は、その部屋で上座にあたるところしかありません。
そのせいでしょうか。
隣席の人たちは「いえいえ。とんでもございません。どうぞ、どなたか、お座りになってください」と、拒否宣言。
「それでは」と、上座に座ろうとする勇気のある人は、誰もいないようで、「どうそ、お座りなって」という言葉が行き交うだけ。
遠慮と配慮をしているのでしょうが、部屋の雰囲気は、悪い方へと進んでいる気がしてしょうがありません。
メンドーになってきた私は、思い切って「そんじゃ、私が」と言いたいところでしたが、残念ながら、生まれて初めてのお茶会で、上座に座る心の強さは、持ち合わせておりません。
結局、その場を救ってくれたのは、男性二人。
埒が明かないと踏んだのでしょうか。
男性の二人連れが上座に座ってくれました。
そのお茶会は、どの部屋も女だらけ。
そこに参加しているってだけで、随分と勇気のある二人だと思っていましたが、上座を巡って繰り広げられていた女の無意味な争いに、終止符を打つ勇気ももっていると知り、拍手を送りたいぐらいでした。
礼儀とか行儀とかって、元々は相手を敬う気持ちからスタートしていると思うのですが、それを厳格に意識し過ぎると、こんな風に、嫌な空気を作ってしまうこともあるんですね。
腹式呼吸のコツを、最近、取得しました。
人間ドックで、様々な検査を受ける際、「腹式呼吸でお願いします」と、検査スタッフから言われます。
腹式呼吸が苦手な私は、「きたっ」と身構え、前日に練習した腹式呼吸を披露します。
すると、「違います。逆です。はい、吸ってー、お腹を膨らませてー。吸うんですよー。お腹、膨らんでませんよー」といったダメ出しを受けることになります。
検査スタッフの指示通りにしたいという気持ちはあれど、呼吸で、お腹を膨らませたり、凹ませたりなんて、できません。
焦っているうちに、もう呼吸なんて考えていられなくなり、お腹を上下させることに集中し、腹筋でもって、なんとかしようと企みます。
そして、検査員が諦めるせいなのか、最低基準をクリアすることもあるせいなのか、なんとか、検査終了にまでこぎつけるのです。
多分、ほかの人の倍は時間がかかっているのではないでしょうか。
大抵、翌日には、お腹が筋肉痛になります。
友人に話したところ、「そんなに根性を見せるところじゃないよ。お腹を意識すればいいんだよ」と言われました。
意識はしてるって。

先日、テレビを見ていたら、健康にいいという運動の実演場面が出てきました。
その運動のポイントは、腹式呼吸をしながら行うということだと、指導員が説明をしました。
その時、ゲストが「腹式呼吸って、どうしたらいいんですか?」と、質問をしました。
いいね、その質問。
思わず、そう、声をかけていました。
指導員が言いました。「口を閉じて、鼻から空気を吸い込んでください。すると、お腹が膨れていきます」
私もやってみます。
すると、確かに、お腹が膨れます。
指導員の指示通り、今度は口を開けて、空気を吐き出します。
これを繰り返しました。
ん?
できてる?
なんと、腹式呼吸ができていました。
っていうか、こんな簡単なコツを、なぜ、私に今まで教えてくれなかったのですか、皆さん。
腹式呼吸してくださいと言うばかりでなく、どうしたら腹式呼吸になるのかを教えてくれればいいのに・・・。
と、八つ当たりですね。
このコツを忘れないよう、毎晩、横になった時には、腹式呼吸の練習をしています。
今度の人間ドックでは、腹式呼吸を嗜む女になってやろうと思っています。
半年近くかかって、ようやく、作品を書き終えました。
すると、どうしたことでしょう。
胃の調子が激変。
長らく続いていた胃の不調は、一気に消え去り、快調そのもの。
ラララ~と、歌の一つも歌いたくなるぐらいの、爽快な気分。
そして、シャレにならないほど大きくなっていた円形脱毛症の、ハゲ部分に、なんと、毛が生えてきたではりませんか。
胃の不調も、円形脱毛症も、どうやら、執筆のストレスのせいだったようです。
とはいうものの、それじゃ、書いている時、辛かったのかというと、決して、そうではなかったんです。
思うように書けず、辛い時も勿論ありましたが、同じくらいの大きさの喜びも、楽しさもありました。
元々、書きたくて、書いていたんですしね。
自ら望んで書いていたくせに、心には相当の負荷がかかっていたのかと思うと、なんだかなぁと苦笑いしてしまいます。

以前にも、同じように、胃の調子が悪いながらも、市販の胃薬を飲み続けるだけで、執筆を続けていたことがありました。
毎日のように胃薬を飲んでいましたが、不快感は消えませんでした。
そのうち、作品を書き終えました。
気が付けば、いつの間にか、胃の不快感はなくなっていました。
2ヵ月後に、人間ドックへ行ったところ、「胃潰瘍になり、それが治った痕がある」と医師から指摘されました。
「この大きさからいって、自覚症状は、かなりはっきりあったはずですが」と言われ、あっ、あれか、と思い出しました。
「仕事の辛い点ばかり気になっているせいで、仮病を使いたい心理が働いて、胃が不調だと偽の信号を送ってきているのかと思ってました」と私が言うと、医師は呆れ顔で「そういう時には、信号が偽か、本物か調べるためにも、ちゃんと診察を受けるべきでしょうね」と、アドバイスを口にしました。
ごもっとも。
不調な時には、病院へ。
基本ですね。
はい。
「平等ゲーム」の文庫が発売になりました。
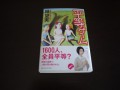
1600人の島民、全員が平等という社会形態を実現した、瀬戸内海に浮かぶ島を舞台にした物語です。
作品を書く度に、なんらかの挑戦をしています。
この「平等ゲーム」でも、挑戦をしました。
その中の1つが、特殊な社会形態の場所で生まれ、育った青年を主人公にしたことです。
心の動き、変化、痛み、哀しみ、喜び・・・そういったものが、通常とは異なります。
登場人物たちは、すべて自分が創り出したものではあるのですが、私がコントロールできるのは、最初だけ。
一度、命を吹き込んだ後は、それぞれの登場人物たちに、任せてしまう、という感覚で書いているため、彼らの声に耳を傾け、見失わないよう、息を凝らして追いかけています。
勝手に、登場人物たちが、動いてしまうんですね。
「平等ゲーム」では、主人公の耕太郎が、次に、どう行動するのか、なにを感じるのかが、予測できず、いつも以上に、見失わないよう、必死で後を追いかけました。
そして、耕太郎が最後に下した結論――。
へぇ、そうすることにしたんだぁと、私はびっくりしました。
自分が書いているのですが、感覚としては、私になんの相談もなく、耕太郎が勝手に結論を出したといった印象でした。
この決断を、読者は、どう感じるでしょうか?
装丁が、単行本の時とは、随分と変わりました。
単行本の装丁も、とても気に入っていたのですが、文庫では、爽やかさと不気味さが絶妙に混在している装丁に変わり、物語性の強い、素敵なものになっていて、こちらも、お気に入りです。