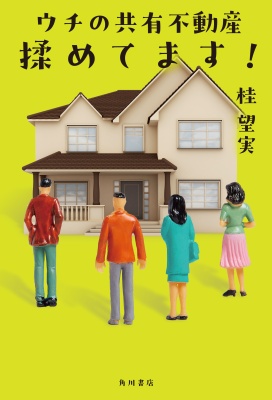小説「ウチの共有不動産揉めてます!」に登場するきょうだいの一人、春馬。
4人きょうだいの長男です。
子どもの頃から、長男だからしっかりしろと、親やきょうだいたちから言われ続けてきました。
長男が皆、しっかりした性格とは限らないというのに。
そんな圧を掛けられて、グレたりする性格でもなかった春馬は、皆が期待する長男の役を演じようとしてきました。
しかし優柔不断で結論を出せない性格の春馬は、しっかり者の長男の役を演じきれません。
ストレスが溜まるいっぽうの毎日です。
春馬は小さな翻訳会社の社長をしています。
ここでもまた皆が期待する社長の役を、必死で演じようとしますが、会社は自転車操業でうまくいっていません。
公私共に演じることを強要されているなかで、どちらもうまくいっていない状況でした。

昔、私がフリーランスでライターをしていた頃、小さな編集プロダクションから仕事を受けていたことがあります。
その編集プロダクションは当時40代ぐらいの男性社長と、女性編集者2名だけで、書き仕事は全て私のようなフリーランスに、外注するというスタイルをとっていました。
仕事はたくさんあるようで次々に依頼がくるのですが、如何せんギャラが安い。
なので「他の仕事の合間に少しだけなら受けてもいっかなぁ」といったぐらいのスタンスでいた私。
他のライターたちも同じように思っていたでしょう。
こっちも生活していかなくちゃいけませんからね。
ある日、その編集プロダクションで打ち合わせをしていたら、社長がクライアントと電話で話している声が聞こえてきました。
マンションの一室でしたから、聞き耳を立てていなくても、しっかりと聞こえてしまうのです。
どうやら無理めな急ぎ仕事をふられている模様。
社長は一旦断るものの、クライアントから粘られて押し切られそうになっている。
そして5分後。
社長はその急ぎ仕事を引き受けていました。
特急仕事であれば、クライアントに通常料金への上乗せを要求するのがフツーだと思うのですが、社長がそのような交渉をしていませんでした。
社長はライターに電話をかけ始めます。
相手の声は聞こえなくても、そんな締め切りでは受けられませんと、断られている様子なのは分かります。
社長はこれから受けてくれるライターを、探し続けるのだろうなと想像し、そうやっていつも忙しそうにしているのに、全然儲かってなさそうな理由を見つけた気がしました。
その後、そこの編集プロダクションとは縁が切れたのですが、風の噂で廃業したと聞きました。
小説「ウチの共有不動産揉めてます!」の翻訳会社はどうかというと・・・社長の春馬が会社をどうしていくべきか悩み、迷い、そして決断するまでの過程が描かれています。
春馬が変わっていく様子を、見届けていただけたらと思っています。
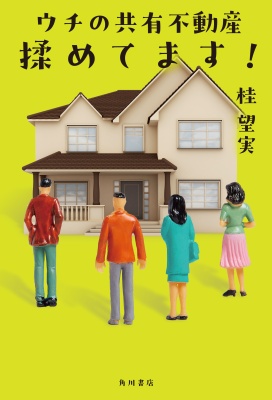
願っていた通りの人生を送っていますか?
「はい」と答えられる人はどれくらいいるでしょう。
かなり少ない、というか稀なのでは。
ほとんどの人は、思い描いていたのとは違う人生を送っているのだと思います。
新刊小説「ウチの共有不動産揉めてます!」に登場する4人のきょうだいたちもそう。
全員が第一希望とは違う人生を送っている。
第二か、第三か。
第三どころか、想定外の人生になっている者も。

長男は小さな会社の社長をしていますが、それは第一希望ではありませんでした。
周囲に強く勧められて断り切れず、渋々社長に就いた長男。
その会社は自転車操業で、お金の心配をする毎日。
そもそも、やりたくてやっているのではないけれど、責任感はあるので、なんとかしなくちゃと思っている。
でも空回り。
長女は中堅規模の病院の看護師長。
周囲から一目置かれている。
部下の看護師に対しては勿論、医師たちにも毅然とした態度で接するから。
気が付けば長女は病院で孤立していました。
長女は望んで看護師になったものの、現状については、なんだかなぁと思っています。
後先考えずに行動する次男は大企業に再就職しましたが、順風満帆とはいっていない。
前妻と暮らしている息子との仲は希薄。
大恋愛の末に結婚した次女は、夫から離婚を切り出されてしまいます。
すったもんだの末に離婚して、実家に戻ります。
個性が強過ぎる母親との暮らしは、ストレスが溜まるいっぽう。
就職氷河期世代の次女は時代のせいで正社員になれず、そこから躓き続きだと嘆きます。
このように希望していたのとは違う人生を送っている4人が、遺産を巡って争うお話が「ウチの共有不動産揉めてます!」です。
きょうだいで争ううちに、それぞれが現状を打破しようという気持ちに。
次の一歩を踏み出そうとします。
彼らの変化と決断を見守りながら、この小説を味わっていただきたいと願っています。
新刊「ウチの共有不動産揉めてます!」を書こうと思ったのは・・・私がこれを体験したから。
まさか共有不動産の揉め事に巻き込まれるとは、思っていなかった私。
次から次に起こる「はぁ?」「なんで?」「どうしてそうなる?」といった展開に、びっくりしているだけの日々が続いていました。
そんな時期に編集者と会食の機会が。
食事もそっちのけで、身に降りかかった事態を熱く語ると、編集者の身近でも色々あったと判明。
共有不動産という落とし穴はすぐ近くにあるのだと分かりました。

これは書かない手はないということで、次作のテーマは共有不動産に決定。
私は執筆前にきっちりとプロットを作る方なのですが、今回は熱い思いがあり過ぎて、物語としてまとまらない。
物語の成形に挑戦している間も、私自身の共有不動産問題はどんどんこんがらがっていく。
現実に引っ張られないように、頭と心を切り替えるのが大変でした。
苦心しましたが、実体験で学んだ共有不動産がらみの法律や判例、業界のことをこの小説の中に盛り込みました。
小説なので物語を楽しんでいただくことが一番ですが、共有不動産についての知識も増えるので、なにかのお役に立てるとしたら、それも嬉しいです。
この小説を執筆中のこと。
スマホにショートメッセージが。
〇〇様のお宅の査定金額が出ましたと書いてある。
迷惑メッセージにしては、間違えた名前を書いてくるというのは、どういうことだろうと思ったものの、そのままスルー。
20分後にまたショートメッセージが。
別の不動産会社からで、〇〇様のご自宅の査定金額をお知らせしますという内容。
そこで気付く。
〇〇さんは自宅の売却を検討していて、査定金額を知ろうとしているのではないかと。
不動産会社のwebに物件情報を入力して、査定金額を知ろうとしたものの、携帯番号を間違えてしまったのでは?
不動産会社に電話番号を教えてしまうと、頻繁に電話が入るので注意した方がいいと、どこかのネット記事に書かれていました。
だから私は自分の電話番号を入力しなくてもいいところにしか、査定依頼をしませんでした。
○○さんはそれを知らなかったのでしょうか。
案の定、翌日2つの不動産会社から携帯に電話が。
〇〇ではないと言って電話を切りました。
〇〇さんが正しい携帯番号を入力していたら、激しい電話攻勢にあっていたのではないでしょうか。
本日「ウチの共有不動産揉めてます!」が発売になります。
この小説はタイトル通り、親から不動産を相続したきょうだいたちの、揉め事が描かれています。
が、それだけではありません。
きょうだい関係や親子関係にも光を当てています。
この小説に登場するのは4人きょうだい。
仲はよくない。
毛嫌いしているというほどではないけれど、それぞれが距離を置いています。
それは幼い頃から。

ただ肩を寄せ合う機会がゼロだったわけじゃない。
個性が強過ぎる母親と、それに負けてない父親が、激しい夫婦喧嘩をすることがありました。
きょうだいが幼かった頃には、こうした時に集まって嵐が過ぎるのを待ちました。
一緒にいることで、心細さや不安を小さくしようとしたのです。
互いを必要とするのはこの時だけ。
それ以外では非交流を貫いてきたきょうだいたち。
成長しそれぞれが実家を出ると、きょうだいたちの距離は更に広がり、ほとんど他人状態に。
それが不動産をきょうだい4人で相続したことで一転。
大金が掛かっていることもあり、本音が炸裂し、それまで知らなかったきょうだいのことを、いやがうえにも知っていくことに。
衝突が激しくなるにつれて、仕舞い込んでいたそれぞれへの不満が噴出。
あの時、あなたはこうだったとか、あの時、なにもしてくれなかったとか・・・。
争いごとの質が変わっていきます。
こうした変化していくきょうだい関係も、この小説の見どころの一つですので、こちらもお楽しみいただけたらと思っています。